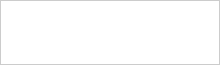築30年から40年位の家ですと、キッチンの壁はまだタイル貼りが主流でした。
しかも下地には小幅板に防水紙、ラス、モルタルが使われてました。
仕様だけ見れば外壁と同じ扱いです。
キッチンの壁だけでも大工さんと左官屋さんとタイル屋さんが関わってました。
タイルも団子貼りという貼り方です。
当時は浴室もタイル貼りが多く団子貼りが普通でしたが、今のタイル職人さん
だと団子貼りはできない人が多いみたいです。
現代では下地は石膏ボードにキッチンパネルが普通で仮にタイルを貼ることが
あっても圧着貼りです。
昔は土壁やモルタル、左官など湿式工法が主流でしたが今はほぼ乾式工法です。
確かに乾式の方が現場も汚れにくく、工期も短縮できます。
しかしそれだけ左官屋さんやタイル屋さんお仕事が少なくなったということです。
建材も良くなってそれほど防水に気を使わなくてもいいようになったのか、室内
で水洗いをするようなこともありません。
シロアリも当時は水回りでよく発生すると言われましたが、今ではそんなことも
なく、勝手口や玄関の方が多いと言います。
トイレや洗面もタイルがよく使われていました。
下地は木ではなくブロック積になっていることもよくあります。
水が回っても腐る心配はないのですが、冬は寒々しいですね。
またリフォームも大変です。
当社では壁を漆喰で仕上げたり、洗面やキッチンも造作することが多くタイルも
よく使っています。
なので左官屋さんもタイル屋さんもほどほど仕事があります。
他ではどうでしょうか。
以前ハウスメーカーの仕事をしていたころはタイルと言えば玄関ポーチくらい、
左官屋さんと言えば全くないか、基礎の巾木の刷毛引き仕上げくらいでしたが。