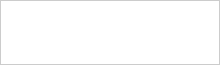改装工事で杉の床板を貼っています。
スギも桧も扱う床板は15ミリと30ミリに分かれます。
そしてランクとして「1等」は普通に節のある床板で「上小」は
ほとんど節がなく、指の先程度の節がたまに混じる程度です。
全く節のないランクを「無地」と言いますがそこでまでこだわる
人はあまりいません。
「無地」と指定するとかなり高価になります。

写真の床板は「上小」と言われるものですが、ほとんど
わかりませんが少し小さな節が混じっています。
「節がない」と説明してしまうとこれがクレームになる
ことがあります。
先日古い書類を整理していたら30年ほど前の見積書が出
てきました。
何気なく木材の見積もりを見てみると、当時の木材単は
現在の単価よりも高価でした。
いまも当時も同じ吉野の木を扱っているのですが、30年前
でこんなに高かったのかと驚きました。
当時の吉野の林業は景気が良かったんですね。
今、儲からないのがよくわかります。
輸入木材のせいでしょうか。
当時は高価だったので木材、柱も今よりも細かく分類されて
いました。
今は単純に、無地、上小、1等ですが、当時の見積もりは柱
に関しては一ム、二ム、三ムと節のない面が何面あるかで単価
が違ってました。
見積図面にもそれぞれの柱に等級が書かれていて柱を1本ずつ
拾い出しいた後がありました。
そういえば大工さんを連れて材木屋さんに行って柱を選んだ覚え
があります。
当時は真壁の部屋が多かったのでそれくらいの手間をかけて準備
をしてました。
それを思うと今は家づくりも簡単になりました。