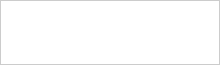宅建業協会の集まりで史跡巡りとして談山神社に来ています。
奈良県桜井市にある神社です。
この神社の前は時々通るのですが訪れるのは初めてです。
かつては神仏習合の寺院「妙楽寺」と一体でしたが、明治初期
の神仏分離令から神社となっています。
その名の由来は中大兄皇子と中臣(藤原)鎌足が大化の改新に
向けて密談(談合)を行ったことから談山神社となっています。
現代でいうところの談合とは少し意味が違うようで「談い山
(かたらいやま)」から来ています。

神社とはいえもとは妙正寺なので塔があります。
日本で唯一の木造十三重塔だそうです。

注連縄と言えば結界を示すものですが、こちらはガイドさんの説明
によると縄は雲を、紙垂は雷を、わらの束は雨を象徴するもので
穀物の豊作を願うものだそうです。
雲と雨は分かるのですが雷はどうしてかというと
大気中には約8割の窒素が含まれています。
この窒素が雷の放電により窒素と酸素が結びつき窒素酸化物を生み出し
それが雨に溶けて降り注ぐことで稲の肥料になるとのことです。
植物の三大要素、窒素、リン酸、カリの窒素です。
恥ずかしながら雷が空気中で植物の栄養素をつくっているとは初めて知
りました。
稲が実るのは雷が多く発生する夏ころ。
昔は雷が稲に実を付けてくれていると思われていたようで「稲妻」
と呼ばれるようになったとか。